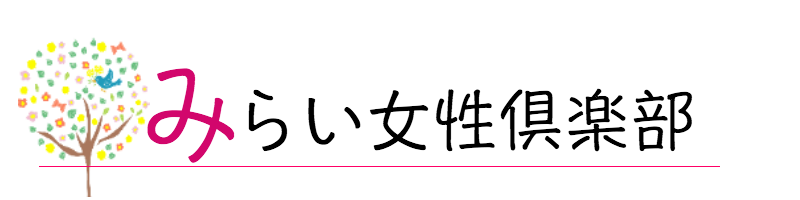ネット銀行と聞くと、多くの方が高い預金金利や優れた利便性を思い浮かべるかもしれません。しかし2024年にマイナス金利政策は終了し、いわゆる「金利のある世界」が戻ってきました。そのため各行の預金金利は上昇してきています。
また、ネット以外の銀行もインターネットバンキングを充実させています。従来型の銀行との差異が縮まるなか、ネット銀行と従来型の銀行を比較します。
※本記事は2024年10月時点の情報です。ご利用の際はご自身で金利や手数料、条件をご確認ください。
ネット銀行の特徴と近年の流れ
ネット銀行は実店舗や自行のATM、紙の通帳がないのが一般的です。家賃や人件費などの コストを抑えられるため、実店舗を有する従来型の銀行に比べてATM利用手数料や振込手数料が安く、預金金利も高めの傾向にあります。また、インターネットで手軽に手続きできる利便性の高さや、提携サービスや独自特典の充実も大きな特徴です。
これらのメリットが支持され、近年のネット銀行の預金残高は増大しています。また個人だけでなく、法人取引の拡大にも力を入れています。
一方で、従来型の銀行も預入金利の引き上げ、インターネットを介したサービスの拡充を計っています。つまり、以前よりネット銀行との違いが縮小しているのです。
そこで本記事では改めて、従来型の銀行とネット銀行を比較します。
※従来型の銀行は「三菱UFJ銀行」「三井住友銀行」「みずほ銀行」を、ネット銀行は「住信SBIネット銀行」「楽天銀行」「PayPay銀行」を参考に比較
ネット銀行と従来型の銀行の金利比較
最初に普通預金と定期預金の金利を比較します。
なお、普通預金や定期預金には条件付きで金利が優遇される場合がありますが、それらは考慮していません。
従来型銀行

ネット銀行

紹介している6行の比較のみにはなりますが、普通預金の金利は横並び、定期預金の金利も従来型銀行もネット銀行はおおむね同じ水準です。決してネット銀行の方が高金利とは言い切れないことがお分かりいただけるかと思います。
ネット銀行と従来型の銀行の手数料比較
続いて、ATM利用手数料と振込手数料と比較します。
ATM利用手数料
従来型銀行
従来型銀行は、自行のATMと提携ATMが利用できます。自行のATMは数が限られるものの、無料で利用できる時間帯があるのが強みです。提携ATMは設置場所が多くて利便性は高いですが、手数料が高いことに注意が必要です。
提携ATMは提携先ごとに利用手数料の設定がさまざまです。そのため、ここでは一部のコンビニATMで取引した場合の利用手数料を紹介します。なお、所定の会員プログラムに入った場合などに対象となる優遇手数料は掲載しておりません。
同じ銀行の提携ATMでも、提携先ごとに手数料が異なるケースがあります。セブン銀行ATM以外は異なるためご注意を。
ネット銀行
ネット銀行はインターネットでの取引を中心にしているため、原則として自行のATMはありません。しかし入出金をしたいときは、大手コンビニ・ゆうちょ銀行等の提携ATMが利用できます。
提携ATM(セブン銀行ATM)の利用手数料は次の通りです。 銀行ごとの違いはありますが、総じてネット銀行の方が手数料は低く、手数料体系もシンプルです。
銀行ごとの違いはありますが、総じてネット銀行の方が手数料は低く、手数料体系もシンプルです。
なお、従来型銀行もネット銀行も、手数料は定められた条件を満たすことで無料利用できるケースが少なくありません。手数料の優遇措置については後述します。
振込手数料
従来型銀行
従来型の銀行で振込する場合、インターネットバンキングやATM、窓口を利用する方法があります。ここではインターネットバンキングとATMの手数料を紹介します。こちらもATM利用手数料と同じく、優遇については考慮していません。
ネット銀行
 従来型銀行のインターネットバンキングやネット銀行の振込は、自行宛なら手数料がかかりません。どちらの場合も他行宛の振込は手数料がかかりますが、従来型銀行のほうが高い水準です。従来型の銀行で、他行あての振込金額が3万円以上となると特に手数料の額が高いといえます。
従来型銀行のインターネットバンキングやネット銀行の振込は、自行宛なら手数料がかかりません。どちらの場合も他行宛の振込は手数料がかかりますが、従来型銀行のほうが高い水準です。従来型の銀行で、他行あての振込金額が3万円以上となると特に手数料の額が高いといえます。
特典による手数料の優遇
利用状況によって無料で利用できるようになったり、所定の会員になることで特典が得られたりすることがあります。各行の代表的な手数料優遇特典の内容を紹介します。また、下記の無料回数は月あたりの回数です。
※特典を受けるためには通常エントリーが必要です
従来型銀行
三菱UFJ銀行 スーパー普通預金(メインバンク プラス)
対象は、スーパー普通預金(メインバンクプラス)口座をお持ちの方です。現在普通預金口座を持っている方は、スーパー普通預金(メインバンクプラス)に変更することも可能です。
・自行ATMの時間外手数料が何回でも無料
・提携ATMの手数料も最大2回まで無料
・三菱UFJダイレクト他行あて振込手数料が最大3回まで無料
※所定の適用条件があります
三井住友銀行 Olive(Oliveアカウント)
Oliveアカウントとは、銀行・決済・証券・保険等の金融サービスを1つのアプリにまとめて管理・利用できるパッケージサービスです。
・自行ATMの時間外手数料が何回でも無料
・SMBCダイレクトの他行あて振込手数料が3回まで無料
・あらかじめ指定した振込先に送金する定額自動送金が無料(別途、定額自動入金の契約が必要)
みずほ銀行 みずほマイレージクラブ
取引状況に応じて特典を受けられるサービスです。手数料の特典を受けるためには、原則としてみずほダイレクトへの登録が必要です。
・みずほ銀行とイオン銀行ATMの時間外手数料が何回でも無料
・提携ATM(コンビニ・イーネット)の時間外手数料が最大3回まで無料
ネット銀行
住信SBIネット銀行 スマプロランク
スマプロランクは、月ごとの利用状況に応じて特典が受けられるプログラムです。ランクは条件ごとに4段階あります。
・ATM手数料が最大20回まで無料
・他行への振込手数料が最大20回まで無料
楽天銀行 ハッピープログラム
楽天銀行の口座と楽天会員情報を連携することでエントリーできる優遇プログラムです。会員ステージが5段階に区切られています。
・ATM手数料が最大7回まで無料
・他行宛振込手数料最大3回まで無料
※楽天ポイントにて振込手数料の支払いが可能
PayPay銀行
・給与受取口座にすることで振込手数料月3回まで無料
各銀行の特典を使えば、従来型銀行でもネット銀行でも、入出金や他行宛振込が無料でできるようになります。手数料の無料回数はネット銀行のほうが多い傾向ですが、利用頻度が月に1-2回程度と少ない方や、平日の無料時間帯に利用できる方は従来型銀行でも手数料はかからないでしょう。
つまり従来型銀行でも、自宅や職場の近くに店舗があり必要な時にすぐ行ける方なら、使い勝手は悪くないと考えられます。一方で、「いつでもどこでもお金のやり取りをしたい」「振込や入出金を頻繁にするので無料回数は多いほうがいい」といった方はネット銀行のほうが向いています。ご自身のライフスタイルにあった銀行を選ぶと、満足度が高くなるでしょう。
ネット銀行の独自特典を紹介
ネット銀行では、関連事業と連携した独自特典もあります。概要を紹介します。
住信SBIネット銀行
<SBI証券との連携によるメリット>
・SBI証券と住信SBIネット銀行の資金移動をアプリで自動化できる
・銀行口座の残高で証券取引が可能
・預金金利の優遇がある
※すべてSBIハイブリッド預金の利用時の特典
楽天銀行
<楽天証券との連携によるメリット>
・普通預金の優遇金利が受けられる
・楽天証券と楽天銀行、それぞれの口座間において無料で自動出入金可能
・ハッピープログラム(優遇プログラム)のランクが上がりやすくなる
PayPay銀行
<PayPayアプリとの連携によるメリット>
・無料でPayPayマネー(スマホ決済)に出金できる
・PayPayアプリで借り入れ・返済、資産運用、保険加入などが行える
ネット銀行・インターネットバンキングはセキュリテイリスクに注意
ネット銀行は手数料が無料になる特典や、関連事業と連携した独自特典に特徴がありました。そこに魅力を感じる方は少なくないでしょうが、利用時の注意点もあります。従来型のインターネットバンキングも同様です。
ネット銀行・インターネットバンキングの注意点
不正利用のリスク
フィッシングサイトやスパイウェア等によるIDパスワードの流出など、セキュリテイリスクがあります。セキュリテイ対策アプリを利用するほか、身に覚えのないメール・SMのURLをむやみにクリックしないようにします。
IDパスワードの紛失
外部からの攻撃とは別に、ご自身のパスワード管理も重要です。IDやパスワードを紛失すると、再取得までアクセスできません。ID・パスワードを自動入力してくれる機能もありますが、頼りすぎに注意します。また、メモアプリや手書きの記録等でID・パスワードの紛失を防止しましょう。
物理的障害
スマートフォンの電池切れ、破損、紛失といった、物理的な障害によって利用できなくなるリスクがあります。またインターネット環境が悪化することで一時的に利用できなくなることもあります。万が一の時のために、現金も持っておくといいでしょう。
まとめ 自分にとって魅力的な銀行を選ぼう
銀行との付き合い方は人それぞれです。出入金や振込が多い方は手数料が重要でしょうし、何かの時に対面で相談したいと考える方は、窓口の有無を重視するかもしれません。「メガバンクだから」「ネット銀行だから」と銀行の事業形態だけで判断するのではなく、特徴や特典を確認したうえで、ご自身にとって最適な銀行を選んでいきましょう。
★2024年10月8日現在の情報です
(執筆:横山晴美)
★家計関連記事一覧はこちら★
みらいに役立つ無料メルマガ配信中
無料相談のお申し込みはこちら