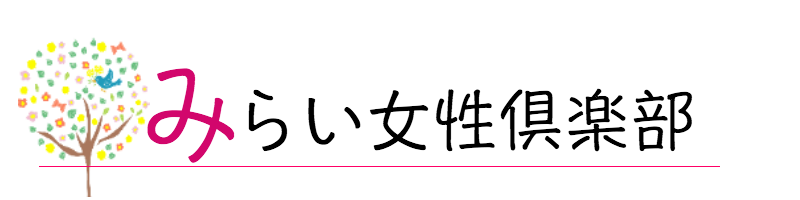みらい女性倶楽部のFP鈴木です。
「会社で企業型DCに入っていますが、iDeCoもやった方がいいですか?」── 先日の企業研修で、こんな質問をいただきました。
確定拠出年金(DC)とiDeCoは併用できますが、そのメリットや注意点は意外と知られていません。今回は、そのときお話しした内容を少しご紹介します。
■企業型DCとiDeCo、両方できる?
はい、併用は可能です。
ただし、毎月の掛金には上限があり、その金額は「5.5万円ー企業がDCに出してくれている掛金」(2万円まで)です。たとえば、企業が1000円拠出している場合、iDeCoに掛けられる金額は1.9万円。なお、2025年の制度改正が施行された後は、企業の拠出額と合わせた上限が月額6.2万円に引き上げられる予定です。
どちらも「60歳以降の資産づくり」という点で同じ仕組みですが、特徴にちがいがあるため、メリットとデメリットを知った上で、併用を検討しましょう。
<企業型DCのメリットと注意点>
運用手数料がかからず、給与天引きで管理が楽なのが大きなメリット。一方で、選べる投資信託の種類が限られていること、ライフプラン支援金などを支給される「選択制DC」の会社の場合は、掛金を増やすほど社会保険料が下がる代わりに、将来の年金額や傷病手当金が減る可能性がある点に注意が必要です。
<iDeCoのメリットと注意点>
iDeCoは、自分で金融機関を選べる自由度が高いことと、掛金全額が所得控除になるため、毎年の所得税・住民税を減らせることがメリットです。ただし、運用手数料が毎月かかることと、金融機関によって商品ラインナップに大きな差があることに注意が必要です。
運用手数料は金融機関によっても大きく異なるため、「iDeCoナビ」など金融機関を比較できるサイトをチェックすると良いですね。
■併用するメリットとは
併用のメリットは、ズバリ、「老後資産を増やせること」と「掛けている間の税金を減らせること」。
企業型DCでは、勤務先の制度を活かして退職金を準備し、iDeCoでは、自分の好みで選んだファンドで長期運用をしながら、今の税金を減らせます。企業型DCの取扱いファンドに対して「信託報酬が高すぎる」「投資したいと思えるファンドが少ない」と感じているけれど、老後のお金をもう少し作りたい方は、ご自身が投資したいファンドを取り扱う金融機関でiDeCo口座を開くと良いですね。
ただし、どちらも60歳までは原則引き出せないため、掛け過ぎて必要な時にお金が足りなくならないよう、バランスが大切です。
■受け取り時の税金の注意点
iDeCoもDCも、受け取り時の税制優遇は同じです。
一括受取 → 退職所得控除の対象
年金受取 → 公的年金等控除の対象
ただし、受け取るタイミングによって控除の使われ方が変わります。
ここでは代表的な2つのケースを紹介します。
1.一緒に一括受取をする場合
企業型DCとiDeCoの老齢一時金を同じ年に受け取ると、その合計金額が退職所得の対象となり、退職所得控除を計算するための「勤続年数」は、積み立て期間の長い方が使われます。
(例)20年間DCをしていて、そのうち10年間iDeCoで積み立てをし、同時に受け取った場合の勤続年数は20年間
もし退職後にDCを受け取らず、iDeCoでの積立を続けると「勤続年数」が長くなり、退職所得控除が増えるケースがあります。
(例)20年間DCをしていて、退職後さらに10年iDeCoを続けて一緒に受け取ると、30年分の控除が使える可能性あり。
2.ずらして一括受取をする場合
受け取る時期をずらすと、あとに受け取る方の退職所得控除が「調整」されます。
(例)40~60歳DCをしていた人が、50歳からiDeCoに加入。60歳の退職時にDCで一括受取、その5年後にiDeCoを一括受取した場合、iDeCoで使える退職所得控除は5年分となる、そんなイメージです。(具体的な計算方法は少々ややこしいので、ここではイメージだけお伝えします)
実際の控除額の計算は複雑なので、受け取り前にはFPや税理士に相談してシミュレーションするのがおすすめです。
企業型DCとiDeCo、どちらか一方を選ぶ必要はありません。
それぞれの仕組みを理解して、家計の中で「今できる範囲」で併用すれば、将来の安心につながります。
60歳以降の自分の資産をどう作るか・・・
少し先の未来を見据えつつ、今、使いたいお金も考えて、将来への備えを検討していきましょう。
☆2025年11月20日現在の情報です
(執筆:鈴木さや子)
★iDeCo関連コラム一覧はこちら★
みらいに役立つ無料メルマガ配信中